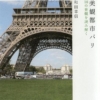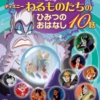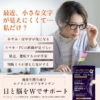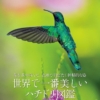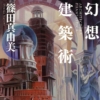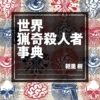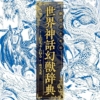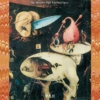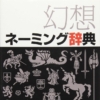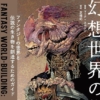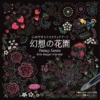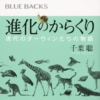🌿【必読の古典】日本の「植物学の父」が説く、自然の見方・感じ方。『植物生態美観〔新版〕』。生態学と景観の概念を生み、桜研究や天然記念物保存に貢献した三好學の「美意識」に触れる。
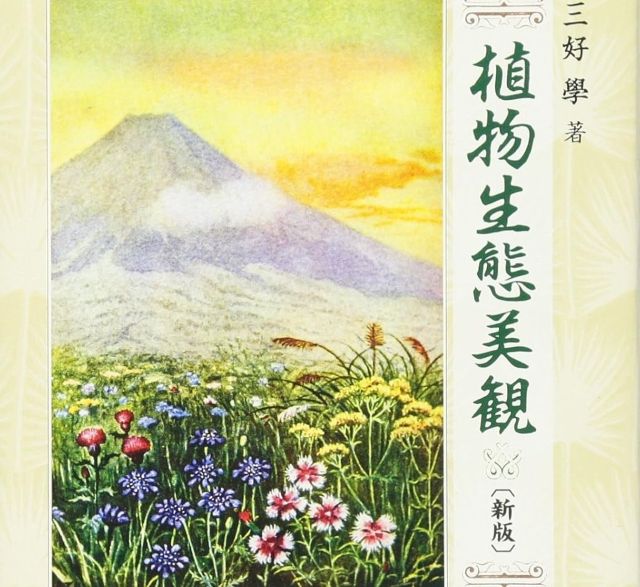
🍃現代の私たちこそ読むべき古典!『植物生態美観〔新版〕』が伝える自然の「見方」
あなたが毎日見ている公園の木や、道端の草花。その美しさを、私たちはどれほど深く理解しているでしょうか? 『植物生態美観〔新版〕』は、日本の近代植物学の基礎を築き、「植物生態学」や「景観」という言葉を生み出した三好學(みよし まなぶ)による不朽の名著です。
本書の魅力は、単なる植物の図鑑や知識の羅列ではない点にあります。三好學は、植物の「美しさ」を科学的・生態学的な視点から体系化し、私たちが自然をどのように捉え、愛でるべきかを問いかけてきます。
科学的知性と溢れる美意識の融合
「植物生態美観」というタイトルが示す通り、本書は植物が持つ形態の美、色の美、香りの美といった要素から、それらが織りなす植物風景の美までを、丁寧に章立てて解説しています。
読み進めるうちに、今までただ「きれいだ」と感じていた植物の姿が、光や水、土壌といった環境の中で生き抜くための「生態的な必然性」から生まれたものだと気づかされます。私自身の感想としては、本書を読むことで、身の回りの自然に対する解像度が劇的に上がったように感じました。例えば、桜の枝ぶりや花の付き方の美しさが、単なる遺伝子の問題ではなく、その土地の環境と長い歴史の中で形作られてきた結果だと理解できるのです。
景観・保全の概念を生んだ先見性
三好學は、日本の桜の研究で知られ、天然記念物保存事業にも尽力した人物です。彼が生み出した「景観」という概念は、自然を単なる資源としてではなく、文化や美の対象として捉え、保護・維持していくべきだという、現代の環境問題やサステナビリティに直結する重要な視点を含んでいます。
本書が新版として現代に復刊されたこと自体が、今こそこの「自然に対する感受性」と「適切な自然管理」の考え方が必要とされていることの証拠でしょう。
知識を携えて自然と対話する
本書は、単なるアカデミックな書物ではなく、自然を愛するすべての人に向けた「自然との対話のガイドブック」です。
「第7章 植物風景の美」や「第9章 季節気象時刻に照応する美」といった章を読むと、私たちがいかに多くの美しい情景を見過ごしているかに気づかされます。この本を読んでから散歩に出かけると、視界に入るすべての植物が、それぞれに物語を持ち、懸命に生きている様子が見えてきます。
自然の見方、感じ方の基本を教えてくれるこの古典的名著は、理系・文系を問わず、豊かな感性と知的好奇心を持ちたいと願うすべての人にとって、書棚に欠かせない一冊となるでしょう。